脳に作用して精神機能や行動に影響する薬を総称して向精神薬とよんでいます。
向精神薬は次のように、大きく4つに分けられています。
|
1.抗精神病薬
2.抗うつ薬
3.抗躁薬、気分安定薬
4.抗不安薬、睡眠薬
それぞれについて説明をします。 |
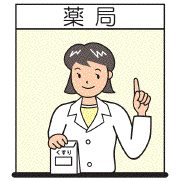
|
1.抗精神病薬
精神病に効く薬という意味です。
統合失調症、非定型精神病、そう病、中毒性精神病などの精神病状態の治療に用いられ幻覚妄想を抑えたり、精神興奮を抑えたりする作用があります。
抗精神病薬は精神機能だけでなく、神経機能(脳)へも強い作用を持っているので神経遮断薬、鎮静作用が強力なことからメジャートランキライザーともよばれています。
統合失調症のための抗精神病薬としては、大きく、定型抗精神病薬(typical
antipsychotics)と非定型抗精神薬(atypical
antipsychotics)に分けられます。
【定型抗精神病薬】
1950年代から発売された旧世代の抗精神薬で、神経遮断薬ともいわれています。この薬は、基本的には統合失調症や、他の疾患における精神病症状の治療に用いられています。作用機序は、中枢性のドーパミン受容体の遮断によって効果や副作用をきたすと考えられています。
幻覚・妄想などの陽性症状への有効性は認められていますが、副作用が強いのも特徴です。
副作用は、多くの患者で急性の錐体外路系副作用(ジストニア、アカシジア、ジストニア、など)が生じます.薬剤性の認知障害(記憶力や思考力の低下)が起こり、発作性知覚変容発作、生活の質(QOL)が低下するといわれています。錐体外路症状としては以下のようなことが知られています。
● パーキンソン症状(パーキンソニズム)
筋硬直、運動減少、振戦、流涎、仮面様症状 前傾姿勢、小刻み歩行など。
服用から1ヶ月前後で出現する。
● アカシジア(静座不能)
下肢のムズムズした感じがあり、座っていられなくなる症状。その場で足踏みをす
ることもある。服用から1ヶ月前後で出現する。
● 急性ジストニア(ジスキネジア)
急性に起こる筋緊張性の運動異常。舌の突出、眼球の上方転移、頚部の後方・側方
へのつっぱりなど。服用から1〜3日で出現する。
【非定型抗精神病薬】
新しい抗精神病薬で、特徴として、従来の定型抗精神病剤に比べて、副作用(錐体外路症状)が少ないこと、陰性症状に対しての治療効果が高いことがあげられています。近年世界的に使用量が増えている薬剤です。
|
★リスパダ−ル(リスペリドン)
1996年導入
★ル−ラン
(ペロスピロン) |
SDA(セロトニン・ドパミン拮抗薬) |
|
★セロクエル
(クエチアピン)
2002年導入
★ジプレキサ
(オランザピン) |
MARTA(多元受容体標的化抗精神病薬) |
|
★エビリファイ 2006年導入 |
ドパミン作用が部分的に働くドパミン・システム・スタビライザーとして作用する薬剤です。
日本でも承認され、注目を浴びています。 |
2.抗うつ薬
抗うつ薬としては、従来からの三環系ないし四環系の抗うつ薬と、新しいタイプの選択的セロトニン再取り込み阻害剤(SSRI)セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤(SNRI)などがあります。
【三環系抗うつ薬】
古くからうつ病の治療薬として使用されています。
主にノルアドレナリンの再取り込み阻害作用により抗うつ作用を示します。
神経伝達物質の一つであるアセチルコリンの働きを抑制する作用(抗コリン作用)
があるため、副作用として、口渇、排尿障害(尿閉)、便秘などがあります。
【四環系抗うつ薬】
ノルアドレナリンの再取り込みを選択的に阻害する一方、シナプス間隙へのノルアドレナリンの放出を抑制している前シナプスα2受容体を遮断することにより、ノルアドレナリンの放出を促進します。
★三環系抗うつ薬は、副作用も強いけれど作用も強いといわれています。
四環系抗うつ薬は、副作用が比較的少ない穏やかな薬といわれています。
【選択的セロトニン再取り込み阻害剤(SSRI)】
SSRIは、前シナプスにおけるセロトニンの再取り込みを選択的に阻害する薬剤です。
SSRIは不安や焦燥が強いうつ病に効果があるといわれ、うつ病だけでなくパニック障害や強迫性障害への適応も勧められています
。
【セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤(SNRI)】
SNRIは主にセロニトニンとノルアドレナリンのシナプス前部のトランスポーターからの再吸収を阻害する薬剤です。
SNRIによりシナプス前部とシナプス後部の間にあるシナプス間隙にはセロニトニンとノルアドレナリンで満たされることでうつ症状に作用します。
3.抗躁薬、気分安定薬
リチウムは、軽症から中等症の急性の躁病患者にはよく効く抗躁薬です。興奮の強い例や重症例には、抗精神病薬の併用が必要になります。
4.抗不安薬、睡眠薬
【抗不安薬】
不安に効果を示す薬物としては、現在より依存性が少なく安全性の高い特異的なベンゾジアゼピン系の薬物が用いられており、次のような作用を有します。
|
1.抗不安作用
2.催眠作用
3.筋弛緩作用
4.抗けいれん作用 |
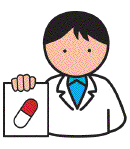
|
抗不安薬は作用期間により短時間作用型(6時間以内、デパス、リーゼなど)、中間型(12〜24時間以内、ワイパックス、ソラナックスなど)、長時間作用型(24時間以上、バランス、セルシンなど)、長時間作用型(80時間以上、メイラックスなど)に大別されます。
【睡眠薬】
睡眠導入剤は6時間以内の長短時間作用型(ハルシオンなど)、12時間以内の短時間作用型(レンドルミンなど)、24時間前後の中・長時間作用型(サイレース、ユーロジンなど)、30時間以上の長時間作用型(ダルメートなど)に分けられます。以上の薬物はすべて脳内で神経の抑制作用を有するGABAの受容体の一部に結合しその働きを強めることにより効果を発揮します。

|